阿蘇くじゅう国立公園
161件の記事があります。
2021年01月06日やまはく・うみはく【月夜のセラピーハイク】
阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう 神代拓馬
皆さんこんにちは!
以前話した「やまはく うみはく」の続きを話したいと思います!
初めに話すイベントは、【月夜のセラピーハイク】です。
このイベントでは、10/31の満月の夜と11/14の新月の夜に、タデ原散策をして頂くプログラムになっています。
※大分朝日放送写真提供
最初に、くじゅう管理官事務所の澤管理官から日本の国立公園の人と自然の関係やくじゅう地域の自然のなりたちについての話があり、参加者の方は真剣に聞いていました。
※大分朝日放送写真提供
管理官の話が終わる頃には日が昇り、いよいよ夜のタデ原を散策します。
くじゅうネイチャーガイドクラブの方とともに星空観察や夜ならではの雰囲気と音を感じました。散策途中の木道で湧水コーヒーとパンを片手に星の解説を聞きます。
プログラムが終わると、参加者の皆さんはとても満足そうに帰られました。
このプログラムには狙いがあります。長者原は紅葉やミヤマキリシマシーズンになると車で駐車場が満車状態になります。しかし、日帰りの方が多く、朝や夜にはほとんどいなくなります。
そこで、国立公園に宿泊してもらう滞在型の利用促進のため、利用者が少ない夜にプログラムを行うことで、周辺ホテルの利用を促すことに繋がると考えました。
また、タデ原を利用することによって、タデ原の自然保全が進むことに繋がるように、そのプログラムの売上金の一部を自然環境保護活動の費用に充てています。
このプラグラムの仕組みが出発点となって、タデ原の自然環境保護の重要性が広く周知できればと思います。
次回は、【はじめてのデイキャンプ】の話をします!
2020年12月15日くじゅう式タイバックアンカー工法とは【くじゅう地域】
阿蘇くじゅう国立公園 大島 将貴
こんにちは。
本日朝からぱらぱらと雪が降り、ようやく冬本番を感じさせる寒さとなってきました。
前回、玖珠美山高校の登山道整備について紹介しましたが、今回は平成30年度に玖珠美山高校が行い、今年の豪雨にも耐えた登山道整備方法について紹介したいと思います。
2年前、玖珠美山高校の高校生、私の担当の班はラグビー部の生徒達が多かったのですが、生徒達と共に4点結束タイプの土留め整備をしました。この工法はくじゅう式タイバックアンカー工法と呼んでおり、地元の自然保護団体、九重の自然を守る会より指導頂きました。
水の通り道になり、登山道側面から崩れていた箇所ですが、4点結束タイプの土留めを2段整備することで崩落を防ぎました。
▲まずは整備の全体像を説明
▲設置した板の後ろに石を敷き詰めていきます
▲リーダーの指示に従いながら、高校生達が石を運びました。ラグビー部の生徒達が頼もしかったです。
今年は7月に豪雨もありましたが、崩れることなくがっちりと止まっています。
こうして比較すると、土留めにはほとんど変化がなく、また、笹の活着も見られます。
この2年間には豪雨や台風、積雪もありましたが、その全てに耐えました。すばらしい耐久性です。
▲平成30年度整備 ▲令和2年度状況
ここで、そもそも「4点結束タイプとは??」
ということで、通常のタイプと、4点結束タイプの比較をまとめています。
▲アンカーとロープも大切ですが、石を詰めて水抜きの確保と設置箇所の選定も重要です
この2つのタイプを、作業の人員や現場の状況などを見て使い分けていますが、使用する資材も異なるため、下見や事前の計画が重要な要素となっています。
そして、先月、熊本、阿蘇事務所から4点結束タイプの視察に来られました。
▲構造の説明
実際に登山道の整備箇所を見た後に、長者原園地にて、解説を行いながら1段制作しました。
アンカーで後ろに引いた後に石を積めていきます。今回は石が多くない場所でしたので足りない部分には木の枝を敷いて対応します。
▲水抜きのため石を詰めていきます
▲石が現場になく、試行的に木の枝を敷いていきます
▲足で圧をかけてもビクともしません。今回の視察を機に熊本や阿蘇などにも広がっていけばと思います。
くじゅうでは7月豪雨で登山道が被害に遭いましたが、地元協議会を通じて、関係機関で連携を行い早期の登山道復旧を行うことが出来ました。
この復旧作業にも今回の4点結束タイプの整備方法が活躍しました。
▲2020年7月30日 ▲2020年12月10日
これも、普段から団体の枠を越えて、共に作業を行い、連携を取って技術の交流や情報交換などを行っていたからではないかと感じています。
今回はくじゅうで行っている登山道整備について紹介しましたが、こういった技術や事例がくじゅうだけではなく、他地域の参考になり、繋がっていければと思います。
2020年12月14日パークボランティアと約340㎏のゴミを回収しました!
阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 姥原悠
11月16日(月)阿蘇山仙酔峡で阿蘇地区パークボランティアと、阿蘇市に協力いただき清掃活動を行いました。
廃屋のロープウェイ駅舎の破損した一部が飛散して好ましくないと一般の方から声が届きました。ここはミヤマキリシマの名所でもあり、開花時期には多くの観光客が訪れます。観賞の妨げにならないよう清掃活動を実施しました。
急な山道を登りながら、飛散物を収集しました。
▲11月の阿蘇は平均気温12度ですが、 ▲1メートルを超えるものもありました
半袖になる人も
ゴミは想定より重く、身体的にかなり厳しい活動でした。
次回実施する際は負担を軽減すべきだと感じました。
▲実施前
▲実施後
約340kgの飛散物を除去することができました。
パークボランティア、阿蘇市の皆さま本当に有難うございました。
5月中旬くらいからミヤマキリシマのピンク色の花が一面に咲きます。
キレイになった仙酔峡にぜひ遊びにきてくださいね。
2020年12月01日玖珠美山高校卒業記念 登山道整備【くじゅう地域】
阿蘇くじゅう国立公園 大島 将貴
こんにちは。
くじゅうでは紅葉も終わり、朝晩の冷え込みも厳しくなってきたところです。
11月9日に、大分県立玖珠美山高等学校3年生の卒業記念作業として、登山道の整備を行いました。玖珠美山高校3年生を主体に、環境省、大分県、九重町、大分県山岳遭難対策協議会、くじゅう地区管理運営協議会、九重の自然を守る会、くじゅうネイチャーガイドクラブ、大分森林管理署のグリ-ンサポートスタッフのサポートのもと、指山登山道の整備を行いました。5班に分かれ、班のリーダー指導のもとで、土留めによる浸食の防止、木階段の設置、劣化したロープの張り替え等を行いました。
▲7月豪雨による土石流に驚きの様子
▲背負子を使って生徒達が資材の運搬を行います
▲先生の指導にも熱が入ります
▲生徒達も階段の杭を打ち込みます
▲完成~!!
生徒、先生、指導するスタッフみんな一緒になり、石を運んだり、杭を打ち込んだり汗を流しました。休憩をまじえながら、作業の途中には生徒達のこれからの進路や高校生活、将来の夢などを語り合い、スタッフも高校生に戻った様な懐かしい気持ちになりました。
昼食を取った後は指山山頂にて記念撮影。
▲三俣山をバックに写真撮影
▲帰り道、きれいに出来上がった道を見て驚きの様子
▲閉会式。玖珠農業高校OBでもある九重の自然を守る会 高橋理事長より温かい挨拶を頂きました
みんな積極的に作業に取り組んでいて、本当に楽しく、良い作業ができました。
玖珠農業高校の時から続くイベントですが、今後もこのような形で地元の若い世代と一緒にくじゅうを守り続けていけたらと思います。
また、これから地元を離れることがあっても、戻ってきたときには、くじゅうの山を見て今日の日を思い出してもらえたらいいなと思います。
玖珠美山高校の皆様、本当にお疲れ様でした!
2020年10月22日秋の草原で出前講座を行いました【阿蘇地域】
阿蘇くじゅう国立公園 アクティブレンジャー 藤田
こんにちは。阿蘇事務所の藤田です。事務所の窓から見えるイチョウが少しずつ色づいています。そろそろ紅葉の季節です。
さて、阿蘇市立阿蘇小学校の小学5~6年生は、毎年、草原の学習に取り組んでいます。昨年12月に阿蘇山上ビジターセンターにて「火山と草原の成り立ち」について学び、今回は秋の野外学習を行いました。
*********************************************
1、「秋の草原の生きものを見つけよう」
2、「草原のススキを使って卒業証書を作ろう」
**********************************************
上記をテーマに、牧野組合が維持管理されている草原に出かけました。
阿蘇地域では通常、草原に入ることはできません。今回は「学習のためなら」と牧野組合から許可をいただいて、消毒のための消石灰を踏んだ上で入りました。
※牛や馬の冬場のエサとなる野草を採る採草地に入るため、消毒効果が確認されている消石灰で靴底の消毒を行い(口蹄疫などの)ウイルスによる感染症などの侵入・発生の予防に注意しました。
昆虫採集と植物観察とに分かれて活動しました。昆虫採集については専門家の先生をお招きし、虫捕り網の使い方などを教わった上で昆虫を捕まえ、先生に名前を確認していただきました。
○貴重な発見
風が強かったため「チョウ」や「トンボ」など捕まえにくかったのですが、「アカギカメムシ」が見つかりました。
アカギカメムシは主に熱帯域か亜熱帯域(マレーシア等)に生息しています。九州では屋久島や種子島などで確認されていますが、寒冷地の阿蘇で見られるのは珍しいようです。
「これは貴重な発見だ!台風で飛んできたかな?」と先生も興奮気味。アカギカメムシは子ども達が熱心に記録をとった後、逃がしました。
植物観察は草原で見られる植物が載っているシートを渡し、班ごとに植物を探し回ります。そこで見つけたものをシートに書き込んでいきます。ワレモコウやアキノキリンソウなど全部で22種類見つけることができました。
今年からタブレットを使った学習が始まり、しっかり記録。
ワレモコウ アキノキリンソウ
カヤネズミの巣も見つけることができました。
最後に、『ススキの卒業証書』の用紙作りのため、原料となるススキの採取を行いました。
ススキをカマで刈り取り、固い茎と葉をより分けます。
集まった材料(ススキ)は柔らかくしてから、自らの卒業証書の紙の原料にします。紙漉きは卒業間近に行う予定です。今から楽しみです!
************************************************
阿蘇草原再生の取り組みでは、阿蘇地域の子どもたちが地域で守り継がれてきた草原について興味を持ち、理解を深めることを目的として、教育現場に導入しやすい草原学習プログラムの提供などを行い、授業をサポートしています。
************************************************
2020年09月30日地域の希少植物を知ってもらうために~【阿蘇地域】
阿蘇くじゅう国立公園 アクティブレンジャー 藤田
こんにちは、阿蘇地域では稲刈りや刈り干し切りなどが始まり、朝晩ひんやりして秋の風を感じます。夜はマツムシなど虫の合唱も聞こえてきます。
さて、阿蘇地域には約1,600種類の植物が生育していると言われています。これは、熊本県内に分布する種の約2割にあたります。そのうち草原に生育するのが約600種類と言われています。しかし、環境の変化などで絶滅の危機にさらされている種もあります。種の保存法では、国内に生息・生育し、絶滅のおそれのある野生生物を「国内希少野生動植物種(以下、希少種)」に指定し、その採取・譲渡等を禁止しています。
令和2年2月に、以前から希少種に指定されていた「ハナシノブ」に加え、阿蘇地域に生育する主な種として、以下の5種が指定されました。
※特定第一種国内希少野生動植物種とは
国内希少野生動植物のうち、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種。
◆ タマボウキ (特定第一種)
※写真のタマボウキはオス。オスメス両方が規制対象
◆ アソサイシン (特定第一種)
◆ ハナカズラ (特定第一種)
◆ ハナシノブ (特定第一種)
◆ ・ヒナヒゴタイ
地元の方に周知するために、この度、環境省でチラシを作成し、
阿蘇郡市内の全戸に、約22,000部を配布しました。
私たちも見たことがない草花もあり、本当に希少だと改めて感じました。
この普及啓発が、生育地を守り、盗掘の防止などにつながることを、切に願っています。
2020年09月30日駆除活動をするわけ 【くじゅう地域】
阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう 神代拓馬
こんにちは。
今回は「ある植物」が環境省の所管地内に生えていることを今年初めて確認したため、駆除を行った話をします。
▼その植物があった場所です▼
事務所全員で早急に「その植物」の駆除に行きました。
その植物はこれです。
答えは、オオハンゴンソウです。
皆さんは、オオハンゴンソウという植物を知っていますか?
オオハンゴンソウは、7月~9月頃大きな黄色い花を咲かせます。
北アメリカ原産の植物で、外来生物法により特定外来生物に指定されています。
生命力は非常に強く、一株当たり1000個以上の種をつけ、主根が2グラム残るだけでそこから再生可能と言われています。
そのため、草刈り機での切り取りだけでは駆除は難しく、手作業でスコップなどでの抜き取り作業で根から取り除かなければなりません。
この時の作業では、約2300㎡の中に7本見つかりました。
少ない...と思われたかもしれません。
でも、たった7株のうちに対処した、ということが大切です。これを「初期防除」と言います。
ところで、今回用意した道具はこちらです。
抜根するためのスコップ、長靴、オオハンゴンソウをいれるためのゴミ袋などありますが...
何故、ざるとバケツがあるのか?それは後にお話しします。
タデ原周辺では、オオハンゴンソウ駆除活動が毎年行われています。
駆除したオオハンゴンソウを袋に入れる際は、花と根を切り取って袋に入れます。
▼今年行われたオオハンゴンソウ駆除活動▼
花摘み担当と抜根担当とに分かれて駆除を行います。
8/9の駆除量 8/30の駆除量
皆さんの協力のおかげで8/9は17袋、8/30は13袋になりました。
帰る際は注意が必要です。
帰る前にしっかりと道具や長靴についた泥を洗い落とします。
この理由は、物に付いた種子や根を落とさずに歩き回ると、オオハンゴンソウが広がってしまう恐れがあるからです。
これが先程のざるとバケツの使い道になります。
タデ原はラムサール条約に登録されている世界的にも重要な湿地です。
しかし、このオオハンゴンソウが湿原の中に入ってしまうと、将来的に希少植物がいなくなり、オオハンゴンソウの花畑が広がってしまうかもしれません。
それを防ぐためにもこの活動は続けられています。
そのため、今まで報告がなかった所にオオハンゴンソウが咲いていたので、早急に駆除を行いました。
オオハンゴンソウの駆除では、駆除して減らすこと以外に、広げさせないことも重要です。
タデ原湿原、くじゅう地域の自然を残していくためにも、継続して活動を行っていこうと思います。
2020年09月24日中岳火口立入り規制の解除に伴いパークボランティアと清掃活動!!!
阿蘇くじゅう国立公園 姥原悠
阿蘇くじゅう国立公園管理事務所の姥原です。
朝晩は涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑い阿蘇です。
先日、9月1日(火)、阿蘇山中岳火口広場の立入規制が約1年半ぶりに解除されました!
長らく近づけなかったため、一部の遊歩道や看板が土砂や灰が積もりひどい状態でした。心地よく見学してもらうため、阿蘇地区パークボランティアと清掃活動を行いました。
(パークボランティアとは国立公園の美化作業や自然解説活動などを行うボランティア団体です)
中岳火口の最新情報はこちらから
http://www.aso.ne.jp/~volcano/
▲久々に間近で火口を見ました。
▲立入禁止看板に火山灰がこびりつき、全く見えません。
▲スポンジでこすると少しずつ文字が浮き上がってきました。
▲大きな看板は時間がかかりました。
▲砂千里ヶ浜の遊歩道にたまった砂を数十メートルに渡って掻き出しました。かなりの肉体労働です。
▲仕上げは箒で掃きます。
▲作業前
▲作業後。心地よく利用できるようになりました。
パークボランティアの会の皆さま、ありがとうございました!
風が強く、火山灰が口や目に入り、ジャリジャリになりました。肉体労働でしたが、砂千里ヶ浜や火口を眺めながらの作業はとても気持ちが良いものでした。
普段見ることのできない火口を間近で見学でき、地球の雄大さを体感できる素晴らしい場所です。この機会に是非見に来てください。
阿蘇火山について、詳しく知りたい方は、阿蘇火山博物館に立ち寄ってみてくださいね。
詳しくは↓
2020年09月18日タデ原湿原 輪地切りを行いました【くじゅう地域】
阿蘇くじゅう国立公園 大島 将貴
こんにちは。
阿蘇くじゅう国立公園と言えば、草原景観が魅力の一つでもあるのですが、この草原の維持のために野焼きが行われています。野焼きは春に行われ、この後の真っ黒になった草原も阿蘇くじゅうを代表する春の景色でもあります。
【野焼き】 【春の野焼き後】
この野焼きを行うために、毎年秋に「輪地切り」を行っています。これは野焼きの時、隣接地の山林や建物に火がうつらないように、草を切っておくものです。また、その後、切った草を燃やす「輪地焼き」を行い、防火帯と呼ばれる幅10メートルほどのラインを作っていきます。
【輪地焼き】 【防火帯】
現在、くじゅうでは猪ノ瀬戸湿原、由布岳、坊ガツル、タデ原湿原・飯田高原周辺、久住高原で野焼きが行われています。昔の形態のまま、地域で野焼きを実行するところもあれば、形態を変え、実行委員会として活動するところなど、様々な歴史をたどりながら野焼きを継続しています。
今回輪地切りを行ったタデ原湿原では、昭和の時代には牛の放牧が行われており、地域での利用がなされていました。地域の共有地として土地を管理し、農繁期以外に各戸が牛を放牧してきました。また、家畜のための干し草、茅葺き屋根を葺き替えるための建材としての利用もなされていました。
【干し草を運搬】※長者原VC提供
以前は地域の暮らしに関わっていた草原ですが、放牧の必要のない農業形態、家畜を飼わない生活形態により草原の利用が減少していき、野焼きが中断されていた時期があります。その時期を経て、地域有志の実行委員会により、野焼きを復活させ、現在も継続してタデ原湿原での野焼きが行われています。
【昭和36年】※長者原VC提供 【令和2年】
上の写真を見ていただくと、59年の時を経ていますが、当時と変わらず草原が広がっています。様々な課題もありますが、当たり前のように受け継がれてきたものを、当たり前に次の世代に受け継いでいければと思います。
野焼きに関しては、今後の野焼き継続に向けて、課題解決に繋がるように輪地切りや輪地焼き等の作業だけではなく、輪地切り箇所の情報をまとめ、整理することを昨年度から行っています。
今回はタデ原湿原と隣接する建物、森林沿いの輪地切りを地域の観光協会有志で行いました。7月の豪雨の影響で地形が変わってしまった場所などあったのですが、無事作業を終えることが出来ました。引き続き10月に輪地焼きを行います。
【輪地切り作業中】
輪地切り、輪地焼きが終わると、山頂付近から紅葉が始まり、冬へと向かっていきます。
少し肌寒い中、すすきの草原に囲まれて歩くタデ原は最高です。
昼間ももちろん気持ちが良いのですが、早朝、夕方は利用者も少なく特別な時間が味わえます。
最後に、今回長者原ビジターセンターより、やまなみハイウェイができる前のタデ原湿原や、湿原に牛が入っていた時代の貴重な写真を提供して頂きました。ありがとうございました。





















































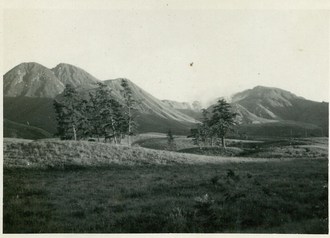




皆さんこんにちは!
以前話した「やまはく うみはく」の続きを話したいと思います!
次に話すイベントは、【はじめてのデイキャンプ】です。
このイベントはタデ原を散策し、その後竹筒で米を炊き、豚汁を作った後にテントを建ててみて、一日キャンプを体験してみようというプログラムです。
▲タデ原を散策(大分朝日放送写真提供)
最初にくじゅうネイチャーガイドクラブの方にタデ原を案内して頂き、希少植物の解説やここで行われている野焼きの重要性を話して下さいました。
▲竹切りや火起こしをしている様子(大分朝日放送写真提供)
歩いてお腹が空いてきた頃に、星生ホテルの借りた炊事場で竹筒で米を炊く体験をしました。竹筒は一から良い長さに切り、自分たちで火を起こし、炊いて行きます。
同時並行で豚汁も作りました。
▲完成品(大分朝日放送写真提供)
うまくできました!
竹で炊いたごはんは、ほんのりと竹の香りがしてとてもおいしかったです。
▲モンベルのテント設置講座の様子
食べ終わると、モンベルの方がテント設置講座をして頂きました。
実際に建ててみると、設置が楽な上にとても軽く、昔のテントよりも扱いやすくなっていました。周囲の方々から「これ買います!」という人も!
今回は、中国出身の立命館アジア太平洋大学(APU)留学生が勉強のため参加しており、準備や受付を手伝って頂きました!(熱心に質問をしています!)
実はこのイベントの主催である大分朝日放送さんもイベントに協力して下さったモンベルさんも環境省のオフィシャルパートナーシップの一員です。また、来て頂いた立命館アジア太平洋大学もオフィシャルパートナーシップの一員です。
今回、オフィシャルパートナーシップの3団体の方が連携したことによって、とても充実したイベントになりました。今後も連携を深めていきたいと思います。