|
|
|
[ ホーム ] → [ とらやまの森バックナンバー ] → [ とらやまの森第8号7ページ ] |
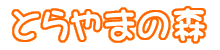
環境省 対馬野生生物保護センター ニュースレター
とらやまの森第8号 |
|
ツシマヤマネコへの生態調査用電波発信機の装着について |
|---|
|
環境庁自然保護局 九州地区国立公園・野生生物事務所 ツシマヤマネコをはじめとする希少な野生生物の保護行政につきましては、日頃より皆様のご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございます。 このたび「ツシマヤマネコを守る会」の会報「ヤマネコ便り」第14号の中で、ツシマヤマネコの保護事業に関する貴重なご意見をいただきました。記事の中では、環境庁がツシマヤマネコ保護増殖事業の一環として生息状況の把握を目的に行なっている生態調査(首輪型電波発信機を装着して電波を追跡するテレメトリー調査)について言及されていますが、環境庁としましてはこれまで説明が不充分であった部分もあると受けとめていますので、調査を実施している立場から少し説明させていただきたいと思います。 環境庁では、1985年に開始された第一次生息特別調査以来16年間に、大学の研究グループ等にご協力いただいている委託調査を含めて合計19頭のツシマヤマネコについてテレメトリー調査を実施してきています(2000年2月現在)。対象は希少な野生動物ですから、捕獲や発信機の装着は綿密な計画を立てて慎重に行なっています。捕獲はオスであることを確認しながら捕る場合を除き、メスの出産期・授乳期には仔ネコへの配慮から実施しないようにしています。発信機の装着は、獣医師の立ち会いのもと、捕獲個体が体重2.5kg以上で歯の状態等から成獣と判断された場合にのみ、首周りに充分な余裕を持たせて行なっており、2.5kg未満で幼獣の場合は獣医師による各種検査後発信機を装着しないまま放逐することにしています。1999年11月13日に対馬野生生物保護センター野外飼育ケージの近くで捕獲されたメスの場合は、初めて捕獲された若い個体でしたが、体重3.11kgで身体各部の状態から成長も一段落した成獣の体格であると判断されたため、調査対象として発信機を装着しました。 首輪型発信機は、調査上必要となる個体識別用の標識としても役立てられており、個体ごとに異なった色の反射テープを付けています。反射テープ自体は発光しませんが、ライトを当てることにより装着個体の存在が明らかになるため、生息上の大きな脅威である交通事故(ロードキル)を防止することも兼ねて貼付しているものです。2000年になってから2月29日現在で既に2頭のツシマヤマネコをロードキルで失っており、事故死を防ぐことは緊急の課題だと考えています。 テレメトリー調査は、動物の行動圏利用・移動・日周期活動・個体関係等に関する研究手段として完全に確立された方法であり、保護管理を目的とした資料を得るために世界中であらゆる動物を対象に実施されています。装着する発信機の重量は、体重の5%以内であれば行動への影響はないという報告があります。現在ツシマヤマネコに使用している発信機は、寿命が約1~2年、重量が40~65gです。装着個体の体重を平均的に3.0kgと仮定すると重量比は2%以下となり、採食等による体重変動の範囲内で重量的な負担はほとんどないといえます。とはいえ、異物の装着が個体へ何らかのハンディになり得ることは理解していますので、首輪の形状・材質・装着具合には細心の注意を払って実施しています。 なお、これまでのツシマヤマネコ生熊調査で首輪型発信機を装着したことによる事故死は一度も起きていません。1999年7月1日に上対馬町小鹿で発見された首輪を装着した死体は、不幸にも猟犬に噛み殺された可能性が高く、死んでから発見されるまでに時間がかかったために首輪装着部位の脱毛が進行していたものと思われます。発信機付け替えのために複数回捕獲されている個体では、首輪による傷害は全く認められていません。 生態調査の調査区域は、調査実施計画に基づいて上県町の一部および上対馬町の一部に限定しており、むやみやたらに捕獲・装着しているわけではありません。装着個体については発信機の電池寿命を考慮の上、継続的な追跡をするため、また定期的な健康診断のために再捕獲・発信機付け替えの努力をしています。これまでの調査研究により未知であったツシマヤマネコの生息環境の特性や社会構造等が少しずつ明らかになりつつあります。上記の調査区域では、保護対策に必要な資料をさらに蓄積するため、細心の配慮をしながら今後も調査を継続していく計画です。 環境庁としましては、ツシマヤマネコのような希少野生種を保存していくための保護事業は調査研究と表裏一体のものであり、保護対象種の状況を科学的に把握する調査研究なしには有効な保護対策は実施困難であると考えています。その上で、ツシマヤマネコ保護のためにはあらゆる努力をしていきたいと思っています。また、地元対馬で民間の立場から行われている保護活動とも密接な協力関係を築いていきたいと考えておりますので、今後とも忌憚のないご意見をいただきますようよろしくお願いいたします。最後になりましたが、ヤマネコ便り第14号の記事「ヤマネコの保護とは何か」を「とらやまの森」に転載させていただくことについて、快く承諾して下さいましたツシマヤマネコを守る会の山村辰美会長に改めて厚く御礼申し上げます。 |
とらやまの森第8号 |
|
|
[ ホーム ] → [ とらやまの森バックナンバー ] → [ とらやまの森第8号7ページ ] |
