|
|
|
[ ホーム ] → [ とらやまの森バックナンバー ] → [ とらやまの森第7号3ページ ] |
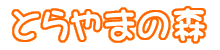
環境省 対馬野生生物保護センター ニュースレター
とらやまの森第7号 |
|
「ヤマネコの生息域でノラネコの調査をしています」 |
|---|
|
※対馬でなんとノラネコの生態調査をしている九大の大学院生平川朝子さんから原稿を寄せていただきました。 平川さんは熊本から子連れで調査にやってくるママさん研究者でもあります。 九州大学大学院 比較社会文化研究科 私が初めて対馬の地を踏んだのは、対馬野生生物保護センターが開所(1997年7月31日)される前日です。かれこれ2年半前ということになります。「ツシマヤマネコがすんでいる島はどんな島なのだろう。」と楽しみに心躍らせて来たことを今でも思い出します。そして対馬は期待どおりの自然にあふれる島でした。私は今のところ調査でしか対馬に来ていませんので、上県の一部しか訪ねていませんが、それでも対馬の自然を十分に満喫していると思っています。 私は山と海と緑が大好きで、大学に進学するにあたり生物学科を選びました。生物の勉強は未知なることの発見の連続で、海に行き、山に行き、顕微鏡を覗き、解剖をしと、とても楽しい勉強でした。また動物や植物のことについて詳しく知っていくにつれて、日々破壊されていく自然を少しでも残したいという思いも強くなりました。大学を卒業した後、高校で生物の面白さや自然の大切さを教えたいと教壇に立ちました。 そのときに生物部の調査としてネコの調査を始めることになりました。ノラネコが同じ場所に40~50頭も集まったところ(エサをやっている人が複数いたのでこのようになったのですが)が学校の近くにあり、ノラネコの社会構造を調べるために調査を始めたのです。本来ネコは単独で生きる動物なのですが、食物資源が十分にあれば、そこに血縁関係からなるエサ場集団が出来ることがわかりました。エサ場の近くに繁殖場所(仔どもを産み育てるところ)と休息場所があれば行動圏(生活する範囲)も狭くなることもわかりました。そのようなことをまとめたいと思い、教員をやめて今の研究科に大学院生として入ったのです。 上記の調査をまとめ終えたちょうどそのころ、ツシマヤマネコの個体数の減少が深刻な問題となり、野外での保護策に加えて人工繁殖の試みがスタートしました。その経緯の中で捕獲した1頭のヤマネコがウィルス性の病気に感染していることがわかり、その解決のためにはツシマヤマネコの研究ばかりでなく感染源と思われるイエネコ(ノラネコと飼いネコの両方を含む)の調査が必要ということになりました。運良く私のノラネコの調査経験が認められて、ツシマヤマネコの研究グループに入れて頂き、イエネコの調査をすることになったのです。ヤマネコが感染していたウィルスを詳しく分析した結果、イエネコが感染しているものと同じものだということが分かり、イエネコからヤマネコに感染した可能性が高いことがわかりました。ウィルス性の病気は一般的に種特異的な病気なので、イエネコとヤマネコは別々の種ですから本来は病気は移らないはずなのですが、それなのに感染しているヤマネコが見つかり、大きな社会問題となったのです。 現在、私は、
などを知るために調査をしています。そのためヤマネコが生息しているところのイエネコの調査をしているのです。日本で一般的なイエネコのウィルス性の病気は6種類あります。イエネコの感染症については「とらやまの森」第3号に福岡市動物園の丸山浩幸獣医さんが書かれていますので、興味がある方はそちらを読まれてください。イエネコの場合、これらの病気に感染したから必ず死ぬというわけではありません。感染しても発病しない個体もいますし、病気を克服して生きていく個体もいます。そのようなネコは見ただけではわかりませんが、他のネコを感染させる恐れが十分にあるのです。 私が調査を始めて1年半あまりで、検査した38頭のうち病気だと判明したネコは11頭(オス7頭、メス4頭)です(1999年11月現在)。交通事故などで死んだりしてこの11頭すべてが現在生きているわけではないのですが、日本の他の地域と比較して決して少ない数ではありません。オスの方が多いのは喧嘩などで感染するからだと考えられます。 ネコは家の中に入り込んで布団の上に寝たり、食べ物をあさったり、家の中におしっこをしたり、悪いことばかりすると言って気に入られていないようです。迷惑だから捕まえて山の方やネコがたくさんいるところに捨ててきたという話を聞いたことがあります。そうしたときに戻ってきた例もあるようです。ネコは、お互いの間で調和の取れた社会関係を作っていますので、そこに別のところからネコを連れてきてもいきなりは入れません。たくさんネコがいるからといってもよそもののネコは溶け込めないのです。すると本来すんでいた場所に戻ってこようとすると思います。心配なことはそのときに別の集落で喧嘩などをして病気をもらってくる(または逆に病気をうつす)ことです。 ネコにそのような病気があるならノラネコは捕まえて全部処分したらいいと思われる方もいるでしょうが、現在自然繁殖しているノラネコも元来は飼いネコだったのです。対馬ではネズミを採るためにほんの少し前まではほとんどの家で飼っていたと聞きました。もともとは人間に飼われていてうまくいっしょに暮らしていたのに、仔ネコが生まれたから、家の作りがしっかりしたからなどの理由で捨てたりしたことでノラネコが増えてきたのではないかと思います。残飯などを海辺や川などに捨ててあるのをよく見かけます。食物資源があるとネコはどんどん増えていきます。無意味にネコを増やすことをやめて、上手に人間との関係が築けたらと思ってしまいます。 自然あふれる対馬、ヤマネコは人が住む前から棲んでいたのでしょうが、イエネコも1000年ほど前からネズミ駆除用として人が飼いはじめたと考えられています。私はこの自然の中で調査をできることを幸せだと思っています。私の調査によって、ヤマネコがいる島で人間と共存していけるイエネコの理想的な状態が提案できたらと願っています。 最後になりますが、イエネコの調査は人の家の中を覗いてまわるようであまりいい気持ちはしませんが、どうかご理解の上、協力をお願いします。また本当にネコに困っているところがあれば、捨てたりする前に、対馬野生生物保護センターや保健所、役場に相談して下さい。 |
とらやまの森第7号 |
|
|
[ ホーム ] → [ とらやまの森バックナンバー ] → [ とらやまの森第7号3ページ ] |
