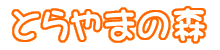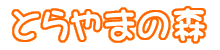ツバキ
今回は、この季節になると咲きはじめるツバキについて紹介しようと思います。
ツバキ科の植物は、対馬には四季を通して7種があります。ヒサカキ・モッコク・サカキ・ナツツバキ・ハマヒサカキ・チャノキの6種は、春から秋にかけて白い花を咲かせますが、冬のヤブツバキだけは、赤色の可憐な花を咲かせます。ここ棹崎公園にはたくさんのツバキの木がありますが、ほとんどがヤブツバキです。
ツバキの現在の品種は、世界中で数千種もあるそうですが、そのほとんどは日本原産のヤブツバキが母種だそうです。
ヤブツバキ
ツバキ科ツバキ属 学名:Camellia japonica 別名:ヤマツバキ
海岸・山中に普通に生える常緑高木。高さは普通5~6mであるが、原生林の中には大きいものもあり10mに達しているものもある。葉は互生し、革質で表面につやがあり、長さ5~12cm、10月~4月に径5~8cmぐらいの赤色の花が咲く。赤い色は変化があり、桃色・赤紫色・白色のものも発見されている。種子から椿油をとる。対馬では全島に分布している。
(対馬では子供が蜜を吸うところからミッチン(蜜椿)とも言われ、ちなみに私もそう呼んでいた。種子のことはかたいし(堅石)、またはカテシともいう。)
ツバキの種子からつくった椿油は、毛髪・頭皮の油分補給に最適です。昔は「髪はカラスのぬれ羽色」と言われたごとく女性の黒髪を保つためにこよなく愛されていたそうです。明治ごろ東京の花柳界で一世を風靡した美女「洗い髪のお妻」は、実は対馬厳原町の生まれで、艶やかな黒髪は故郷から取り寄せた椿油で手入れをされたそうです。
私が子供のころは対馬の大半の家で椿油をつくっていたと思いますが、最近では対馬でも椿油をつくっている人は数少なくなってきています。そこで現在でも全てご自分で作業をしておられる島居由里子さんのお宅でお話を伺い、昔ながらの方法での椿油の作り方の行程を実際に教えていただきましたので、紹介したいと思います(島居さんは対馬野生生物保護センターの清掃作業員でもあります)。ちなみに対馬では、椿油をつくることを「カテシのアブラをスメる」と言うそうです。
1.種子をつぶす

山で集めて拾ってきたかたいしをカラウシ(かたい物を杵でつぶす石臼)に入れ、粉になるまでつぶします。
2.粉をふるう
粉になったかたいしをスイノウ(ふるい)で何度もふるって、粉と殻を分けます。
3.粉を蒸す
こまかくなった粉を、蒸し器にかけ約1~2時間半ほど蒸します。
4.蒸し終わったものを絞ると椿油の完成

蒸したものをシュロの木の皮に包み入れ、その上に万力(ジャキー)(圧力をかけて絞り出す道具)とさらに石の重りを使って絞り出します。これを用途によって何度か濾過して、できあがり。
このように1~4の行程をへてやっと椿油の完成です。
椿油の使用法
- (A)毛髪・頭皮の油分補給、整髪
- (B)天ぷらなどあげる食用油
- (C)機械・大工道具などの錆止め
- (D)化粧品や薬品の原材料
参考文献「対馬の自然」浦田明夫・國分英俊共著 <AB>
|