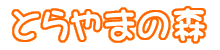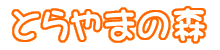ツシマヤマネコの自動撮影について
野生動物の生息状況を調査する方法は対象動物や目的によって様々であるが、その中に直接観察法というのがある。その調査は読んで字のごとく対象を直接観察する方法で、種や個体を知る上では最も確実かつ有効な手段であり、動物をナマで観察できるという満足感もある。しかしながら、かなりの体力と忍耐が必要であり、対象動物の生態や生息環境によっては不可能な場合もある。そこで自動撮影調査が登場してくるのだが、それは観察者の代わりにカメラという見張りを立てて、動物に与える影響を最小限にしながら少ない労力で終日観察出来るというメリットがあり、近年の映像撮影機器の発達によって幅広く取り入れられている調査方法である。
当センターでツシマヤマネコのモ二タリングのために行っている自動撮影調査の装置には、三脚方式とボックス方式の2つがある。三脚方式は、三脚にカメラとセンサーを取り付けてそのまま野外の調査ポイントに設置する。その前を通ってセンサーに反応するもの(ヤマネコ・テン・イタチ・シカ・ネズミ・イノシシ・ウシ・鳥類・人間・クルマなど)を幅広く撮影することが出来るため、そこを利用する種の調査やヤマネコの生息分布域の把握のために利用している。ボックス方式は、自作のアクリル箱の中にカメラをセットして、箱に入ってきたヤマネコのクローズアップを撮影することにより、ヤマネコの個体識別(額の縦縞の紋様等を見る)をしながら個体の状態の確認を容易にするものだ。
自動撮影調査をする上で最初にやらなくてはならないことはカメラ等の改造である。この改造は、市販のフルオートコンパクト防水カメラと熱感知式のセンサー(よく玄関先などにある人が通ると体温を感知して明かりがつく仕組みのもの)を配線でつないで、センサーが反応するとシャッターがレリーズする仕組みにするというような細かい作業だ。1台ン万円もするカメラやセンサーをバラしたり穴を開けたりするため注意深くやらないといけないし、壊さないように完璧な防水を施してやることも忘れてはならない。しかし、最近カメラの調子が悪くなることが多い。やはり野ざらしはきつい。メーカーが専用コネクターを備えた壊れないのを作ってくれたら、売れると思うんだがなぁ。
次に野外にカメラを設置するポイントを選ぶわけだが、適当に置いてもヤマネコが写るわけはなく、やはり事前に下調べをした上で痕跡(フン・足跡・食痕)がある場所とか、痕跡はなくても頻繁に利用してそうな場所(獣道があったり、水飲み場があるようなところや食物となる小動物が多そうなところ)に置くのが望ましい。

←↓ボックス方式で撮影された別個体です。皆さん、顔の模様の違いで識別できますか?
2000/10/02 棹崎ポイント

2000/11/14 田の浜ポイント
あとはどうやって装置まで誘引するかだが、基本的には対象動物が興味を持つ「におい」が有効だと思う。誘引のために「餌付け」することは、動物本来の行動を変える等の悪い結果を引き起こす可能性があるため慎重を要するところだ。エサを使う場合はそれだけに依存することのないように量を調整するなどして、出来るだけ自然状態を損なわないように配慮しなくてはならない。
現在、長崎県が中心となって自動撮影調査によるツシマヤマネコのモニタリングを対馬全島27ポイント(上島:20ポイント、下島:7ポイント)で行っているが、上島の上対馬町・上県町・峰町・豊玉町では今年度もヤマネコが写っていて生息分布が確認されている。しかし、下島の厳原町・美津島町では努力の甲斐なく未だに写真では確認されていない状況である。フンなどの痕跡はあるのだから、何とかして写真で確実な生息の確認をしたいものだ。さらに当センターの近くの山中にもセンター開所以来自動撮影装置を設置しているが、ここでは頻繁にヤマネコが現れており、前号までで紹介したテレメトリー調査の結果と併せることによって、繁殖の状況等かなり詳細な生態学的データが集積されてきている。
最近のカメラの小型高機能化、センサーのハイコストパフォーマンス化により、自動撮影装置も進んできているが、防水デジタルカメラの利用によるフィルムの廃止と撮影枚数の増加など、もっといい装置ができないものかと考える日々である。よいアイディアがあれば是非アドバイスいただきたい。 <Mk・T2>
|