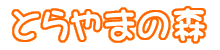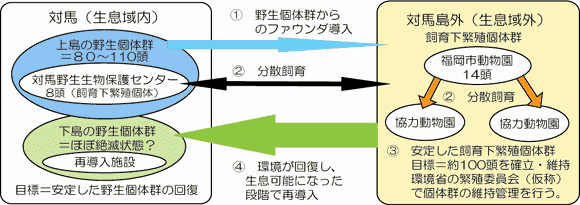安定した野生個体群回復のための飼育下繁殖の目的
- 緊急避難的な種の保存=ノアの箱舟 →生息地で安定して暮らせるようになるまでの避難
- 野生個体群保護対策の補完(再導入など)
- 科学的データの収集と解析 →ヤマネコの保護対策に応用
- ツシマヤマネコを全国の人に知らせる
現在の飼育下個体群事業の課題
- 長期的な飼育下繁殖実施計画づくり
- 資源の不足(資金・施設・人材)
- 市民への情報提供と社会的理解を得る
- 近親交配の問題(ファウンダの不足)
- 再導入の準備(再導入施設など)
飼育下繁殖個体群の確立と再導入が可能になるまでの流れ
- ファウンダ導入 1996年から現在まで、合計6頭の野生個体が飼育下繁殖の原資(ファウンダ)として福岡市動物園に導入され、そのうち4頭のヤマネコが繁殖に成功しました。しかし、この数は近親交配を避けるためには十分ではありません。
- 分散飼育 2000年にはじめて成功して以来順調に繁殖が進み、飼育下繁殖個体群は現在までに22頭になりました。しかし、このまま福岡市動物園だけで飼育を行うと、万一、感染症の流行や事故が起こった場合に、一度に多くの個体を失ってしまう可能性があります。また、飼育個体数がさらに増えれば、施設、資金、人材もさらに多く必要となります。
それらの問題を解決するためには、対馬野生生物保護センターや複数の協力動物園などで分散してヤマネコの飼育下繁殖を進める必要性が指摘されています。現在、環境省では平成16年発表の再導入基本構想に基づき、(社)日本動物園水族館協会とツシマヤマネコ飼育下繁殖の協力体制づくりに向けた話し合いを行っています。
- 安定した飼育下繁殖個体群の確立 近親交配を避け、「ファウンダの遺伝的多様性の90%を100年間維持する」という世界的な基準を満たした状態が「安定した飼育下繁殖個体群」とされます。国際ワークショップでのシュミレーションでは、ツシマヤマネコでその基準を満たすためには、約100頭まで飼育下個体群の数を増やし、それを維持する必要があることが示されました。少し増えたからといって無計画に再導入を行うと、飼育下の個体群を多数失ってしまう危険性があるため、100頭前後を長期間維持する必要があります。
- 再導入 ひとたび安定した飼育下繁殖個体群が確立できれば、100頭以上に個体を増やし、ツシマヤマネコの生息がみられなくなった地域に再導入することも可能になります。そのためには、その再導入する地域でヤマネコが暮らせるように、自然環境の回復・改善を行うことが前提になります。再導入を成功させるためには、さらにヤマネコの生態についても調べる必要があります。その調査結果は、野生個体群の保護にも活用することができます。
また、繁殖や野生順化訓練を行うための再導入施設を対馬内に設置する必要もあります。
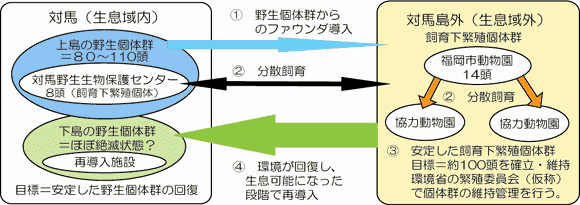
|