報道発表資料
【通知】平成19年度奄美大島におけるジャワマングース防除事業の実施結果と平成20年度事業の実施計画について(お知らせ)
2008.5.23 那覇自然環境事務所
環境省那覇自然環境事務所では、奄美野生生物保護センターを拠点として、平成12年度から奄美大島においてジャワマングース駆除事業を行っており、平成17年度からは、外来生物法に基づくジャワマングース防除事業(以下、「防除事業」という)を実施しています。
(1)平成19年度防除事業の実施結果について
平成19年度防除事業の捕獲作業においては、合計137万わな日あまりの捕獲努力を投入した結果、780頭のマングースが捕獲、除去されました。平成19年度の捕獲数は、平成18年度までの年間捕獲数の1/3以下に減少しました。これまでの防除事業の成果により、ジャワマングース(以下、「マングース」という)の生息密度が低下していることが考えられます。
(2)平成20年度防除事業の実施計画について
平成20年度防除事業では、筒型捕殺わなの捕獲効率を上げるための改良を早期に進め、奄美マングースバスターズを32名から37名に増員し、林内での捕獲作業を拡充することにより、さらに高い捕獲圧をかけることで、マングースの生息数の一層の低減化と分布域の縮小を目指していきます。また、マングース探索犬の試験的導入など新たな防除技術の開発も並行して行います。
1.平成19年度防除事業の実施結果について
- (1)奄美マングースバスターズによる防除の体制等
- 奄美大島におけるマングース分布域の外縁部や林内などでの捕獲作業の充実のために、平成17年度から「奄美マングースバスターズ」と称する専任の作業チームを編成し、作業地域を拡大しながら平成19年度末までに32名体制にして、分布域の全域で筒型捕殺わなと生け捕りわなによる捕獲作業を実施した。 筒型捕殺わなは、ルリカケス等が進入できないように加工を施して改良した形状のものを6月から導入した。マングース分布域の山中にわなルートを設定し、ケナガネズミ等の在来種が生息する地域においては混獲を防止するために生け捕りわなを、混獲の可能性が低いと考えられる地域においては筒型捕殺わなを設置した。すべてのわなの設置地点をGPSで取得し、わな1個ずつを管理する体制とした。
- (2)実施結果等
-
- 【1】実施期間
- 平成19年4月1日から 平成20年3月31日まで
- 【2】実施区域
- 奄美市(名瀬地区、住用地区)、龍郷町、大和村、宇検村
- 【3】捕獲努力量(わな日: のべわな日数=わなの数×日数)
- 平成19年度: 1,372,369わな日(暫定)
- 平成18年度: 1,051,026わな日
- 平成17年度: 630,822わな日
- 平成16年度: 318,715わな日
- 【4】マングース捕獲数
- 平成19年度: 780頭
- 平成18年度: 2,713頭
- 平成17年度: 2,591頭
- 平成16年度: 2,524頭
- 【5】結果概説
-
- 平成19年度における捕獲努力量(のべわな日数)は、平成18年度よりも約30%多い1,372,369わな日(暫定)となった。また、マングース捕獲数は780頭で、平成18年度(2,713頭)と比較すると約70%減少した。
- 捕獲努力を増大させているにもかかわらず、捕獲数が大きく減少していることから、奄美大島におけるマングースの生息密度及び生息数はかなり低下したと考えられる。 一方で、混獲防止のために施した筒型捕殺わなの改良により、マングースが捕れにくくなって捕獲効率が低下していることも明らかになった。
- マングース及びクマネズミ以外の混獲は、平成18年度に比べて大きく減少した。改良された筒型捕殺わなでは、ケナガネズミ1頭のほかヘビ類3頭、オカガニ1頭が捕獲されたのみで、ルリカケスの混獲は発生しなかった。 また、生け捕りわなでは、マングースの生息密度が低いと考えられる地域を中心に、アマミトゲネズミ52頭、ケナガネズミ23頭、アカヒゲ17羽などの捕獲が確認された。死亡が確認されたアマミトゲネズミ3頭及びアカヒゲ4羽以外は全て放逐した。
- 地域別にみると、最も捕獲の多かったのは奄美市名瀬地区(451頭)で、龍郷町(138頭)や奄美市住用地区(89頭)を大きく上回っていた。
- マングースの分布域(捕獲された範囲)に顕著な減少は認められないが、龍郷町北部、奄美市住用地区、宇検村などの地域では捕獲数が非常に少なくなり、分布域の外縁部ではマングース個体群の孤立分断化が一層進行したと考えられる。
- 平成12年度から平成19年度末までに、有害捕獲、駆除事業、防除事業を通じて、奄美大島において総計約3万頭のマングースを捕獲、除去したこととなる。
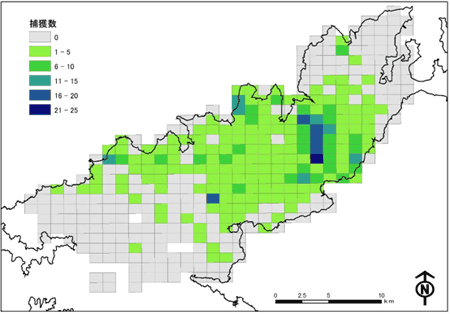
図1. 平成19年度マングース捕獲数
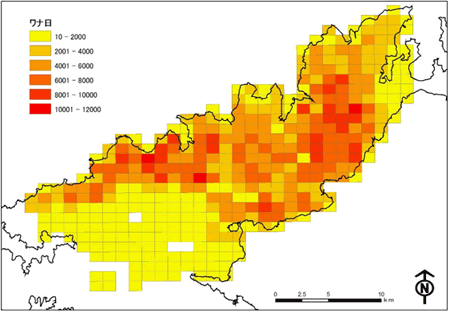
図2. 平成19年度のべわな日数
| 捕獲数 | オス | メス | 性別不明 | わな日 | CPUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10 | 0 | 8 | 2 | 13,745 | 0.07 |
| 5月 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10,910 | 0.03 |
| 6月 | 12 | 1 | 3 | 8 | 52,745 | .02 |
| 7月 | 34 | 2 | 2 | 30 | 154,824 | 0.02 |
| 8月 | 59 | 3 | 1 | 55 | 151,940 | 0.04 |
| 9月 | 46 | 2 | 0 | 44 | 122,534 | 0.04 |
| 10月 | 82 | 2 | 1 | 79 | 142,083 | 0.06 |
| 11月 | 113 | 5 | 10 | 98 | 139,221 | 0.08 |
| 12月 | 139 | 4 | 1 | 134 | 150,199 | 0.09 |
| 1月 | 148 | 4 | 1 | 143 | 126,375 | 0.12 |
| 2月 | 88 | 4 | 1 | 83 | 155,329 | 0.06 |
| 3月 | 46 | 1 | 1 | 44 | 152,464 | 0.03 |
| 合計 | 780 | 28 | 30 | 722 | 1,372,369 | 0.06 |
| 捕獲数 | オス | メス | 性別不明 | わな日 | CPUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奄美市名瀬 | 451 | 14 | 15 | 422 | 598,863 | 0.08 |
| 奄美市住用 | 69 | 3 | 5 | 61 | 105,633 | 0.07 |
| 龍郷町 | 138 | 1 | 0 | 137 | 295,128 | 0.05 |
| 大和村 | 121 | 9 | 10 | 102 | 355,251 | 0.03 |
| 宇検村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17,494 | 0.01 |
| 合計 | 780 | 28 | 30 | 722 | 1,372,369 | 0.06 |
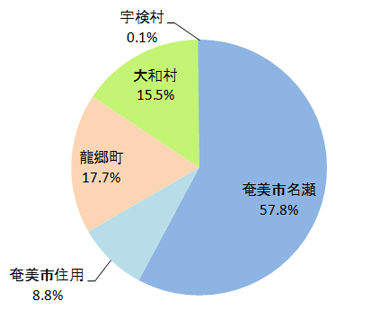
図3 市町村別のマングース捕獲割合(%)
2.平成20年度防除事業の実施計画について
- (1)事業の目標
- 防除実施計画4年目の事業を効果的に実施するため、効果を上げている筒型捕殺わなのさらなる改良と作業体制の整備に重点をおく。また、わな以外の防除方法として、マングース探索犬の育成等、防除のための新たな技術開発も並行して進める。
- (2)防除事業の実施内容
-
- 【1】筒型捕殺わなの捕獲効率改善
- 現在使用している形状のものよりもマングースの捕獲効率が高く、在来種の混獲を防止できるわなを早期に開発し、現地作業に導入する。また、筒型捕殺わなと生け捕りわなを地域と時期によって効果的に使い分け、マングース分布域のさらなる分断化と縮小を目指す。
- 【2】捕獲作業の実施体制等
- 奄美マングースバスターズは人員の体制を37名に強化して作業チームを編成し、投入する捕獲努力量は年間180万わな日以上を目標とする。 また、これまで十分な捕獲作業等が実施されてこなかった岩崎産業株式会社の社有林内については、奄美マングースバスターズと同様の手法により、同社による捕獲作業を実施してもらうことを予定している。このことによって、マングース分布域の全ての地域で効果的な防除を実施することが可能になると考えられる。
- 【3】マングース防除効果の評価
- 平成20年度末にマングース分布域における存否確認のためのモニタリング調査を行い、生息個体数を推定する。また、マングースの生態及び捕獲結果を考慮した数理モデルを構築し、防除効果の予測・捕獲戦略の検討を行う。
- 【4】在来生物種の生息状況等モニタリング調査
- 捕獲作業と並行して、アマミノクロウサギ、イシカワガエル、ヘビ類、ルリカケス等のモニタリング調査を実施する。また、センサーカメラ等を用いて在来動物種の生息状況を確認する。
- 【5】マングース探索犬の訓練と導入
- ニュージーランドで利用されている外来捕食者探索犬の幼犬2頭を導入し、マングース探索犬としての訓練技術を習得する。また、国産の狩猟犬を利用した探索犬の開発についても作業を進める。平成20年度の訓練と試験的導入ののち、平成21年度中に実用化できる体制を整備する。
- 【6】新たな防除手法の検討
- ダイファシノン系薬剤のマングースへの給餌法の確立及び薬剤による殺マングース効果及び在来生物種や生態系への影響を評価する。また、マングースの水銀無機化作用機序ブロックによって有機水銀中毒を誘発し、マングースに特異的な防除法を確立できる可能性があるため、この研究を進める。
- 【7】普及啓発
- 奄美大島におけるマングース防除事業の重要性について、地域住民はもとより広く国民及び国際的な理解を得るため、印刷物、行事、講演、マスメディアを通じた広報、国際協力研修等の場において情報を公開し、普及啓発を行う。