2013年8月13日
3件の記事があります。
2013年08月13日子どもパークレンジャー!【屋久島地域】
屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川
みなさん、こんにちは!
屋久島自然保護官事務所の水川です。
今回は、8月3日(土)に実施した「平成25年度 第1回 子どもパークレンジャー」についての報告です!
子どもパークレンジャーは、国立公園の自然保護官(パークレンジャー)の仕事を子ども達が体験しながら自然と触れ合い、自然保護や環境保全の大切さを学ぶ活動です。
第1回目の今回は、屋久島国立公園の海域公園地区に指定されている塚崎海岸で、タイドプール観察を行いました。
参加者は、島内の小学4~6年生18名です。
タイドプールでは、ビンゴゲームをして様々な生き物を探し、見つけた生き物とその場所を、自分たちでスケッチしたタイドプールと海岸線の地図に
書き込んでいきました。
子ども達は、見つけた生き物を箱メガネに入れたり、シャコを軍手で釣ろうとしたりと、思い思いのスタイルで観察を楽しんでいました。
最初、水に濡れないように観察をしていた子どもも、最後には肩までどっぷり水に浸かって、みんな夢中で海の中をのぞいていました!

お昼休憩の後は、パークレンジャー体験です!
看板磨きチームと海岸清掃チームに分かれて、パークレンジャーの仕事を体験してもらいました。
看板磨きチームには、看板を綺麗に拭いてもらい、柱に防腐塗料を塗ってもらいました。
海岸清掃チームには、海岸のゴミをたくさん拾ってもらいました。
普段体験できない作業に、みんな興味津々の様子でした。

塚崎海岸での活動の後は屋内に戻り、自分たちで描いたタイドプールと海岸線の地図に、見つけた生き物を描き加えた、タイドプールマップを班毎に作成しました。
見つけた生き物のイラストを模造紙いっぱいに描いて、最後は、どんな生き物がいたか、お気に入りの生き物や初めて見た生き物について発表しました。
中には、韓国から流れ着いたゴミを初めて見て印象的だったと発表する班もありました。
そして最後に、私から国立公園とパークレンジャーの話をして全ての活動を終えました。

左の写真は完成したタイドプールマップを持って発表する様子。
班毎にとってもカラフルで楽しいマップを作ってくれました!
右は、国立公園とパークレンジャーについて解説する様子。
炎天下の中、海で泳いで疲れていたと思いますが、最後までしっかりと話を聞いてくれました!
今回の子どもパークレンジャーでは、屋久島の海、その海に暮らすたくさんの生き物と触れ合いました。
そして、すばらしい自然がある国立公園と、国立公園の自然を守り多くの人に利用してもらうために働くパークレンジャーについて知ってもらえたと思います。
この体験をきっかけに、自然の中で大いに遊んで、自然をもっと身近に感じ、
大切にしてもらいたいと思いました。
屋久島自然保護官事務所の水川です。
今回は、8月3日(土)に実施した「平成25年度 第1回 子どもパークレンジャー」についての報告です!
子どもパークレンジャーは、国立公園の自然保護官(パークレンジャー)の仕事を子ども達が体験しながら自然と触れ合い、自然保護や環境保全の大切さを学ぶ活動です。
第1回目の今回は、屋久島国立公園の海域公園地区に指定されている塚崎海岸で、タイドプール観察を行いました。
参加者は、島内の小学4~6年生18名です。
タイドプールでは、ビンゴゲームをして様々な生き物を探し、見つけた生き物とその場所を、自分たちでスケッチしたタイドプールと海岸線の地図に
書き込んでいきました。
子ども達は、見つけた生き物を箱メガネに入れたり、シャコを軍手で釣ろうとしたりと、思い思いのスタイルで観察を楽しんでいました。
最初、水に濡れないように観察をしていた子どもも、最後には肩までどっぷり水に浸かって、みんな夢中で海の中をのぞいていました!
お昼休憩の後は、パークレンジャー体験です!
看板磨きチームと海岸清掃チームに分かれて、パークレンジャーの仕事を体験してもらいました。
看板磨きチームには、看板を綺麗に拭いてもらい、柱に防腐塗料を塗ってもらいました。
海岸清掃チームには、海岸のゴミをたくさん拾ってもらいました。
普段体験できない作業に、みんな興味津々の様子でした。
塚崎海岸での活動の後は屋内に戻り、自分たちで描いたタイドプールと海岸線の地図に、見つけた生き物を描き加えた、タイドプールマップを班毎に作成しました。
見つけた生き物のイラストを模造紙いっぱいに描いて、最後は、どんな生き物がいたか、お気に入りの生き物や初めて見た生き物について発表しました。
中には、韓国から流れ着いたゴミを初めて見て印象的だったと発表する班もありました。
そして最後に、私から国立公園とパークレンジャーの話をして全ての活動を終えました。
左の写真は完成したタイドプールマップを持って発表する様子。
班毎にとってもカラフルで楽しいマップを作ってくれました!
右は、国立公園とパークレンジャーについて解説する様子。
炎天下の中、海で泳いで疲れていたと思いますが、最後までしっかりと話を聞いてくれました!
今回の子どもパークレンジャーでは、屋久島の海、その海に暮らすたくさんの生き物と触れ合いました。
そして、すばらしい自然がある国立公園と、国立公園の自然を守り多くの人に利用してもらうために働くパークレンジャーについて知ってもらえたと思います。
この体験をきっかけに、自然の中で大いに遊んで、自然をもっと身近に感じ、
大切にしてもらいたいと思いました。
2013年08月13日口永良部島清掃活動その②! 【屋久島地域】
屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川
みなさん、こんにちは!
屋久島自然保護官事務所の水川です。
前回の口永良部島活動報告その①から1ヶ月が経ってしまいました…。
しかし!その①を書いたからには、その②も書かなければ!!
ということで、遅れての報告になりますが、第二弾としてオオキンケイギクの駆除とサソリモドキについて報告します。
オオキンケイギクは、5月から7月にかけて鮮やかな黄色の花を咲かせるキク科の植物です。
九州各地の道端などでよく見られ、屋久島の県道沿いでもたくさんのオオキンケイギクが咲いていました。
一見コスモスに似たかわいらしい花ですが、自宅の庭や花壇に植えることはできません!
オオキンケイギクは、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の「特定外来生物」に定められており、栽培、運搬、販売などが禁止されています。
いったん定着すると周りの在来種の生育場所を奪ってしまい、日本の生態系に重大な影響を及ぼします。
このオオキンケイギクは口永良部島にも定着しており、今回の活動で一部を駆除することになりました。
島の方にもお手伝いいただき、空き地を埋め尽くすほどぎっしり生えたオオキンケイギクを抜いていきました。

左の写真はオオキンケイギク。右はオオキンケイギク駆除作業中の様子。
作業を進めていると、なにやらお酢のようなすっぱい臭いが辺りに漂ってきました。
気のせいかと思い、黙々と作業を進めていたのですが…やっぱり臭う!
一面に生えていたオオキンケイギクを抜き、地面が見えてきた頃、ついに犯人が現れました!
サソリモドキです!!

正式にはアマミサソリモドキ(Typopeltis stimpsonii )といい、九州南部から沖縄にかけて分布しています。
夜行性で昆虫や土壌動物を補食し、危険を察知すると、おしりから液を噴射します。
この液は、成分の80%が酢酸で、手や顔に着くと危険です。
作業中に漂っていたすっぱい臭いの正体は、サソリモドキが噴射した液でした。
大学時代を沖縄で過ごした私ですが、恥ずかしながらサソリモドキは1~2回しか見たことがなく、今回口永良部島で出会えて、改めてサソリモドキのフォルムに惚れ惚れしました。
今回の口永良部島活動では、登山道の標識の塗り直し等も行いました。

パークボランティアの方2名という少ない人数での活動で、様々なハプニングもありましたが、なんとか活動を終えることができました。
皆さん本当にお疲れ様でした!
屋久島自然保護官事務所の水川です。
前回の口永良部島活動報告その①から1ヶ月が経ってしまいました…。
しかし!その①を書いたからには、その②も書かなければ!!
ということで、遅れての報告になりますが、第二弾としてオオキンケイギクの駆除とサソリモドキについて報告します。
オオキンケイギクは、5月から7月にかけて鮮やかな黄色の花を咲かせるキク科の植物です。
九州各地の道端などでよく見られ、屋久島の県道沿いでもたくさんのオオキンケイギクが咲いていました。
一見コスモスに似たかわいらしい花ですが、自宅の庭や花壇に植えることはできません!
オオキンケイギクは、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の「特定外来生物」に定められており、栽培、運搬、販売などが禁止されています。
いったん定着すると周りの在来種の生育場所を奪ってしまい、日本の生態系に重大な影響を及ぼします。
このオオキンケイギクは口永良部島にも定着しており、今回の活動で一部を駆除することになりました。
島の方にもお手伝いいただき、空き地を埋め尽くすほどぎっしり生えたオオキンケイギクを抜いていきました。

左の写真はオオキンケイギク。右はオオキンケイギク駆除作業中の様子。
作業を進めていると、なにやらお酢のようなすっぱい臭いが辺りに漂ってきました。
気のせいかと思い、黙々と作業を進めていたのですが…やっぱり臭う!
一面に生えていたオオキンケイギクを抜き、地面が見えてきた頃、ついに犯人が現れました!
サソリモドキです!!

正式にはアマミサソリモドキ(Typopeltis stimpsonii )といい、九州南部から沖縄にかけて分布しています。
夜行性で昆虫や土壌動物を補食し、危険を察知すると、おしりから液を噴射します。
この液は、成分の80%が酢酸で、手や顔に着くと危険です。
作業中に漂っていたすっぱい臭いの正体は、サソリモドキが噴射した液でした。
大学時代を沖縄で過ごした私ですが、恥ずかしながらサソリモドキは1~2回しか見たことがなく、今回口永良部島で出会えて、改めてサソリモドキのフォルムに惚れ惚れしました。
今回の口永良部島活動では、登山道の標識の塗り直し等も行いました。

パークボランティアの方2名という少ない人数での活動で、様々なハプニングもありましたが、なんとか活動を終えることができました。
皆さん本当にお疲れ様でした!

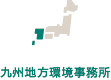
以前のAR日記にて夏バテになりそうと言ったものですが、前言撤回します。
快適そのもの、最高に涼しいです!!
さて、そんなえびの高原で、先日「えびの高原自然教室」を行いました。
えびの高原周辺の植物や動物、歴史をじっくり勉強しようというイベントです。
何気なく「歩く」だけならば40分ほどで一回りできるコースを、なんと2時間30分もかけて、講師の解説に耳を傾けたり、鳥の鳴き声が聞こえたらしばらく立ち止まったり、ゆっくりじっくりと歩きました。
(アカマツ、ノカイドウ、ミヤマキリシマは序の口で、キリシマミズキ、ノリウツギ、リョウブ、ミズナラ、ナツツバキ、ウリハダカエデ、イソノキ、コバノクロズル、ススキ、キリシマアザミ、モウセンゴケ、ヒカゲノカズラ、マンネンスギ、などなどの植物の蘊蓄をたくさん教えていただきました。)
覚えきれないほどのたくさんの詳しい解説で知的好奇心を刺激された参加者のみなさんは、童心に返ってヒカゲノカズラを叩くと出る胞子に目を輝かし、モウセンゴケの花を発見しては喜びの声をあげ、ノリウツギやリョウブの違いを花や葉や木肌に至るまで一生懸命に観察していました。
ミヤマキリシマやノカイドウの開花時期には、黙っていても多くの利用者で賑わっている、えびの高原ですが…
今回のイベントによって、特に目立った花が咲いていなくても、解説者といっしょに歩くことで十分に楽しめる場所であることが伝えられたと思いました。
見つけて、触って、嗅いで、かじって、聞いて、とおもいっきりえびの高原を感じた一日でした。