2013年8月 6日
2件の記事があります。
2013年08月06日新城島インドクジャク銃器駆除【石垣地域】
西表石垣国立公園 石垣 アクティブレンジャー 仲本
最近の石垣は、毎日暑い日が続き、雨が降らないので農作物や水不足が心配になります。みなさん熱中症にも十分ご注意下さい。
さて、八重山諸島では、リゾート施設、小学校などから飼育個体が逃げ出したものと考えられるインドクジャクが野生化しており、現在、小浜島・黒島・石垣島・新城島・与那国島で繁殖しています。
インドクジャクは、キジ科の鳥でインドやスリランカなどに自然分布しています。トカゲ類や昆虫のほか、植物の芽・種子・果実を主に採食し、農作物に被害を与えることから、外来生物法の特定外来生物に準じる対策が必要な外来生物として、要注意外来生物に選定されています。

インドクジャクのオス
今回、八重山猟友会の皆さんや新城公民館の方にご協力いただき、新城島で猟犬や銃器を用いて、インドクジャクの駆除作業を実施しました。

駆除作業前の様子
新城島は竹富町にある島で、上地島と下地島の2つの島を総称しています。下地島にはインドクジャクは生息していませんが、上地島には、1969年にリゾート関連企業が宿泊施設で観賞用として飼育していた飼育個体が逃げ出し、野生化していました。その後、平成18年から23年に掛けて129羽を駆除し、現在は5個体以下まで減少していると考えられ、根絶が近い状況となっています。上地島は面積1.76平方キロメートルと小さな島ですが、集落以外の多くの場所は木や草がうっそうと生い茂っています。さらに、クジャクは木の上や草陰にジーと隠れて気づかれないようにしているため、1個体を見つけ出すことも一苦労です。
今回の駆除作業では、目撃情報の多い島内西側を重点的に朝から夕方まで捜索しましたが、1個体を発見するも、逃げられてしまい駆除することが出来ませんでした。これまで銃器駆除以外に捕獲罠を設置して捕獲を試みていますが、警戒心が強い個体が残っているため、罠に掛かる個体が少なくなっているのが現状です。島内にいる個体は、残り数羽と思われるため、再び増える前に駆除を実施していきたいと考えています。

新城島(上地島)内の様子
外来生物は、小さな島の中であっても一度繁殖してしまうと、駆除し、根絶するのに膨大な費用と労力を要します。生き物を飼育しているみなさんは、外来生物法の被害予防三原則である「入れない、捨てない、広げない」を心にとめ、責任を持って生き物を大切に飼育していただきたいと思います。今回の駆除作業に同行して、改めて外来生物を根絶することの難しさを痛感した一日となりました。
さて、八重山諸島では、リゾート施設、小学校などから飼育個体が逃げ出したものと考えられるインドクジャクが野生化しており、現在、小浜島・黒島・石垣島・新城島・与那国島で繁殖しています。
インドクジャクは、キジ科の鳥でインドやスリランカなどに自然分布しています。トカゲ類や昆虫のほか、植物の芽・種子・果実を主に採食し、農作物に被害を与えることから、外来生物法の特定外来生物に準じる対策が必要な外来生物として、要注意外来生物に選定されています。
インドクジャクのオス
今回、八重山猟友会の皆さんや新城公民館の方にご協力いただき、新城島で猟犬や銃器を用いて、インドクジャクの駆除作業を実施しました。

駆除作業前の様子
新城島は竹富町にある島で、上地島と下地島の2つの島を総称しています。下地島にはインドクジャクは生息していませんが、上地島には、1969年にリゾート関連企業が宿泊施設で観賞用として飼育していた飼育個体が逃げ出し、野生化していました。その後、平成18年から23年に掛けて129羽を駆除し、現在は5個体以下まで減少していると考えられ、根絶が近い状況となっています。上地島は面積1.76平方キロメートルと小さな島ですが、集落以外の多くの場所は木や草がうっそうと生い茂っています。さらに、クジャクは木の上や草陰にジーと隠れて気づかれないようにしているため、1個体を見つけ出すことも一苦労です。
今回の駆除作業では、目撃情報の多い島内西側を重点的に朝から夕方まで捜索しましたが、1個体を発見するも、逃げられてしまい駆除することが出来ませんでした。これまで銃器駆除以外に捕獲罠を設置して捕獲を試みていますが、警戒心が強い個体が残っているため、罠に掛かる個体が少なくなっているのが現状です。島内にいる個体は、残り数羽と思われるため、再び増える前に駆除を実施していきたいと考えています。

新城島(上地島)内の様子
外来生物は、小さな島の中であっても一度繁殖してしまうと、駆除し、根絶するのに膨大な費用と労力を要します。生き物を飼育しているみなさんは、外来生物法の被害予防三原則である「入れない、捨てない、広げない」を心にとめ、責任を持って生き物を大切に飼育していただきたいと思います。今回の駆除作業に同行して、改めて外来生物を根絶することの難しさを痛感した一日となりました。

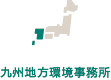
さて、台風が過ぎてしばらく経った7月23日(火)に石垣市立富野小中学校の小学生の皆さんとコーラルウォッチを行いました。富野小では、平成18年度と19年度の2年間、子どもパークレンジャー(JPR)の活動として地域の海に関する学習を行っており、平成19年度には日本で初めて学校の授業にコーラルウォッチを取り入れました。その活動はJPR終了後も学校の取り組みとして継続しています。さらに今年度からはPTAの方々が協力した新たな体制で実施するため、環境省職員もサポートすることになりました。今年度は5月に事前学習と1回目の調査を終えており、今回は2回目のコーラルウォッチとなります。
地域によって同じコーラルウォッチでも少し方法を変えています。八島小の児童と実施する真栄里海岸でのコーラルウォッチは、見つけたサンゴをランダムにチェックしています。一方の富野小ではチェックするサンゴを決め、毎回同じサンゴを調べます。適度な深場があり、特徴的な形のサンゴがたくさんある富野の海岸ならではの方法です。児童達と一緒になり、校長先生が調べるサンゴも決まっています。
3グループに分かれて行う富野小のコーラルウォッチ、今回私は高学年の担当となりました。児童にチェックするサンゴを覚えているか尋ねると「覚えてな~い」と少し気のない返事・・・。石垣の小学校は7月19日に終業式を終え、既に夏休み中。そんな中集まったので少しテンションが低めだったようです。それでも海に出てみると児童たちはちゃんと調べるサンゴを見つけてチェック。あまのじゃくな年頃なんですね。
調べたサンゴは前回の調査よりも色が濃く元気だったようです。気温が上がるとサンゴの健康度が少し落ちてしまうことが多いので、児童達は先生と一緒に「7月は気温が高いのになんで?」頭をひねっていました。(恐らく台風によって海水がかき混ぜられ、水温が下がったのでしょう。児童たちにはまだ内緒です。)
写真1.チェックするサンゴを見つけて早速調査。高学年となると手際がいいです。
コーラルウォッチの後は勝手に生きもの探しが始まります。今回のターゲットはウミウシ。女の子でも平然と手のひらに乗せてしまいます。ただ、ウミウシの種類によっては食べた生きものの毒をそのまま蓄える種類もいるようなので、不用意に触らないようにしましょう。
写真2.探すとたくさん見つかったムカデミノウミウシ
写真3.アオボシミドリガイでしょうか?でも触角が見当たらない・・・不思議です。
ご存じの方はぜひokironc@coremoc.go.jp(春口宛)までご連絡ください!
富野小では9月までの期間に月1回のコーラルウォッチを予定しています。夏場を中心に年に数回の調査を実施してきて7年目。これまで貯め続けた結果から、今年何かがわかるかもしれません。また、今後石垣のサンゴに大きなダメージがあった場合、最初に気付く小学生はきっとこの子達でしょう。モニタリングを根気強く継続している先生方にも感服します。私たちも自然の豊かさと海の楽しさを伝えつつ、サポートしていきたいと思います。